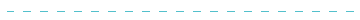
ステップ
ベッドに腰を下ろしたアラミスは、左腕をゆっくりと回した。肩をのぞき込むように見つめながら、腕の感覚を確かめる。
(……よし、これならどうだ)
一度動きを止めてから、今度は大きく、そして少し速く回す。
背中側へ回した時に、ほんの少しだけ、痛みが走った。アラミスは僅かに顔をしかめる。
(でも、この位なら、また剣が持てる。……やれます、フランソワ)
アラミスは左手首を撫でながら、微笑んだ。
その時、馬のいななきが近付いて来た。聞き慣れた二つのその音は、威勢よく止まった。もちろん、アラミスの家の前に。
外から聞こえる声に導かれ、アラミスは窓へ駆け寄る。
「二人とも、入って来いよ!」
元気そうなアラミスの様子に、アトスは明るく驚いて、頬を緩ませた。
「頼まれていたものを持ってきたぞ。どうだ、調子は?」
そう言ってからアトスは、机の上に包みを置き、紐を解いていった。その中には、本が四冊。どれも厚さがあった。
「ありがとう。かなり戻ってきているんだ。この調子なら、全部読み終える前に、復帰できそうだ」
「そう言わず、ゆっくり休めよ。まだ戻ってきたばかりなんだし。
ところで、頼んでいたというのはその本か。暇つぶしか?」
「じっと休んでいてもする事もないしな。まあ、左手に気をつけて、少しずつ読むとするよ」
「うーん、それもなんだか疲れそうだが」
そう言って、ポルトスも持ってきていた包みを取り出す。大きなそれは、開く前から香ばしい匂いを帯びていた。
包みが開かれると、その香りは部屋中へ、大きく広がる。
「こりゃあすごいな、鹿か?」
「ああ、見舞いだからと言って、丸焼きにしてもらったんだ。焼きたてだぞ。みんなで食べようぜ。取り分けてくるよ」
ぶどう酒も持ってきたしな、と付け足して、ポルトスはその大きな皿を、意気揚々と運んで行った。
食べる事にかけては、実に用意周到な巨漢の親友。そんな彼の背中を見送るアトスとアラミスから、思わず笑みがこぼれていた。
それからアラミスは、テーブルの上に置かれた本を、一冊手に取った。
「こっちもありがたいな。これだけあれば……」
アラミスの言葉は不自然に止まった。一度手の動きを止めてからすぐ、吸い寄せられるように、本をパラパラとめくる。少し年期の入ったその紙は、角が少し痛みだしていた。
「アトス、これ、ダンスの本じゃないか」
「ん?」
言われて、アトスはアラミスの横から、本をのぞき込む。それは確かに、社交界での踊りについて書かれた、それも実践的な内容のものであった。
「ああ……そう言えば、こんな本もあったかな」
随分と昔のものだ。アトスは懐かしそうに言ってから、他の三冊にも目を留める。
「君は何でも読んでくれるだろうから、あまり考えなしに取って来たのだ。そうか、こんな本も混じっていたか」
テーブルに片腕を付くアトスに、アラミスはまた笑みをこぼした。
「驚いたよ。アトスが踊る姿、なんだか想像つかないな」
「そうか?」
「最後に踊ったのはいつだ?」
「さあていつだったかな……まあ、たしなみで、簡単に踊るくらいなら、今もできると思うが」
彼の話を聞きながら、アラミスは最後にフランソワと踊った時を思い出していた。
彼らはいつも森の中で会っていた。故に、踊る時に流れる演奏などない。
しかし、そよぐ風が、水のせせらぎが、彼らの音楽となっていた。自然に包まれた二人は、未来の幸せに思いを馳せながら、心を躍らせて踊っていた。
時が経つのも忘れ、ただ幸せを噛みしめていた。
「アラミス、ちょっと体を貸せ」
「えっ」
アラミスの返事を待たずに、アトスは手を伸ばす。
伏し目がちに昔の事を思っていたアラミスは、不意に右腕を引かれて顔をあげる。気付けば彼女は、アトスと体を密着させていた。
「こうだったか」
アラミスの右手を取って、アトスは軽く、流れるように踊る。アラミスの怪我を気遣うように、優しいリードで室内を一周。
彼の歩調に合わせつつも、アラミスは抗議の声を挙げる。
「おいちょっと待て、なんで俺が女役なんだ」
「どうだ、意外に覚えていただろう」
アラミスの抗議など意に介さず、アトスは楽しげに笑う。彼は動きを止め、彼女から一歩離れた。
「なんだなんだ、楽しそうだな」
隣室から丸焼きを切り分けたポルトスが現れた。
彼は大事そうに、料理をテーブルに置いた。そして、丁寧に皿を並べていく。
「アトスも踊れるんだな」
「な、ポルトスも意外だと思うだろ?」
悪びれもせず話す二人に、アトスは肩をすくめた。
「二人とも、俺をなんだと思っていたんだ。
そういうポルトスこそ、どうだ?」
「よしきた」
皿を全て置いたポルトスもやはり、アラミスの手を取り、彼女の腰に手を添える。
「よしきたじゃないぞ、また俺が女役か」
その表情には、諦めの色が浮かんでいた。
「へへ、任せておけって。こうやってだな……」
アラミスをリードしようとしたポルトスはだが、足をもつらせてしまった。
「うわっ」
ダンスは始まらないまま、ポルトスはアラミスにのし掛かるように倒れ込んでしまう。無論、アラミスもバランスを崩して、一緒に床へ導かれる。
「大丈夫か!?」
アトスは、二人に駈け寄った。
ポルトスもすぐに体を起こし、自分の腕の下にいるアラミスの様子を伺う。
「すまんアラミス、大丈夫か!?」
床に頭をつけたまま、アラミスはくすりと微笑む。
「ポルトス、今のじゃダメだ。これじゃあ、ご婦人方はたちまち逃げ出してしまうなあ」
そして左腕を気遣いながら、アラミスは立ち上がる。それでもなお痛いところはないかと尋ねるポルトスに大丈夫だと告げてから、アラミスは先ほどの本を手に取った。
数秒の間だったか、じっと本を見つめてから、何かを思いついた様子で顔をあげた。
「アトス、この本、又貸ししても良いか?」
「ああ、良いぞ」
「ア、アラミス!?さっきのは偶然さ。俺は本当はもっと」
「おいおい、誰がポルトスに又貸しすると言ったんだ」
「んっ?」
アラミスは少しだけ意地悪く、だが涼しげな笑顔を、ポルトスに向ける。ポルトスは、不思議そうにアトスの顔を見た。それは、アトスも同じであったが。
「ダルタニャンだよ。……コンスタンスと、な」
言ってから、アラミスは片目をつむって見せる。
「なるほど!」
合点がいったポルトスは、すっきりした声をあげた。
「あいつこそ、きっと踊り方を知らないだろうからな」
アトスは椅子に座り、頬杖を付いてにこっと笑った。
「……ダルタニャン」
他の二人に聞こえない程小さく呟いてから、アラミスはその本をベッドの上に置いた。それは、布団に小さく沈む。
この場にいる全員が、彼がイギリスでの任務を無事に終えて戻ってくる事を、信じている。三人は今、お互いに同じ思いを共有しているのだ。
「よし、取り分けたぞ。来いよ、アラミス」
明るい声。見れば、ポルトスも席に着いている。
彼らの視線と、そして暖かい匂いの導きを受けて。アラミスは優しく頷いてから、軽やかな足取りで二人のところへ近付いて行った。
その間ポルトスは、自前の酒を各々のグラスに注いでいく。心地良い音に、友人たちの気持ちも綻んでいく。
必ず戻って来い。そうしたら、手取り足取り、ダンスを教えこんでやろう。
願いと希望を乗せて。グラスが甲高く愉快な音を奏でたのは、間もなくの事であった。
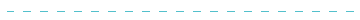
長めの後書き
首飾り事件で、三銃士&ジャン&コンスタンスがパリに帰ってからの話です。休息アラミスと愉快な親友たちでした。みんなよく笑ってますね。
アニメディア5月号にあった「三銃士はダルタニャンの身の上を心配しつつ、大人の日常を味わっている」という記事と(読み直しあります)、
アニメージュ3月号にあった、「コンスをリードして楽しく踊るダル&それを楽しそうに見ている三銃士のイラスト」から考えた話です。
そして私の書く話のポルトス、食べ物に関連している率は2011年6月現在100%の気がします。ポルトスは食事のために、食事はポルトスのために…。
ダンスを踊るちょっとおふざけなアトスとか、イメージ違うかな…とも思いましたが、もう、勢いでやっちゃいました(笑)。
"大人の日常"なのか何なのか、若干疑問ですが、まあ、あの、愉快な三人なのでしたー!(無理やりシメる) (2011.6.4)
![]()