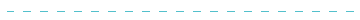
ラビリンス
馬を駆る男は、背後からのしつこい追跡を振り切らんと、速度を速めた。しかし、追っ手はみるみる男に迫り来る。
「うおっ」
不意に、馬がいなないて倒れた。乗り手の男も導かれるままに、地面に体を叩きつけられる。
力を入れて、痛む体を起こす。見れば、馬の足に短剣が突き刺さっていた。馬は小さく悲鳴を上げながら、がくがくと体を震わせている。
「くそっ」
痛みが疼く半身を気遣う間もなく、男は立ち上がる。人気のない通りだが、隠れられるような場所も見当たらない。
短剣を投げた追跡者は馬から降り、男の前に立ちはだかる。右手には、剣がしっかりと握られていた。丁寧に磨かれている長い剣は、地面に太陽の光を反射させている。
男もまた短剣を取り出した。肩を上下させながら、目の前の追跡者と向き合う。
男は、追跡者の姿を、頭から爪先まで舐めるように見てから、下卑た笑みを浮かべた。そして、その黒い口を開く。
「……!」
男の言葉を聞いた追跡者は、弾かれた様に男を襲う。突然の攻撃に、男の短剣はあっさりと、その手から離れた。
「ぐっ……!」
円を描いて落下する短剣を目で追ったほんの一瞬に、男の腹部を激痛が襲う。それは何度も、何度も。追跡者の拳が、みぞおちにしっかりと沈んでいた。胃液が逆流していく感覚が、喉に、舌に、頬に、伝わってきた。
その頬も、右側から強い力に襲われた。痛みは、頭部まで瞬く間に広がっていく。
よろめく男の胸ぐらが、天へ向かって力強く引き寄せられる。それからその背は、反動と追跡者を伴って地面へ強く叩きつけられた。
立て続けに与えられる衝撃と激痛に、男は、声を発する事が出来ない。気付けば、追跡者は男の腹をぐっと踏みつけ、馬乗りになっていた。
男は、苦しみながらも目を開いた。そこに飛び込んできたのは、感情を宿さぬ冷たい瞳と、剣の切っ先であった。それは、彼の顔面へ向かい、勢いよく加速して迫る。
「ひいっ」
男はそこで意識を手放さざるを得なかった。だから、自分が斬られたのか否か、その時はよく分からなかった。
男は、斬られずに済んでいた。
振り下ろされる剣の、動きが止まったからだ。正確には止められた、というべきか。
剣が握られた追跡者の右手はだが、横から伸びた白い手袋により、その動きを封じ込められていた。
白い手の、その先の顔を見る。視界に飛び込んできたのは、よく見知ったその姿。
「アトス……」
その名前を呼ぶと同時に、全身から力が抜ける。
こめかみから一筋の汗が流れた。その汗を皮切りに、彼女の全身は不快な感覚に包まれる。
先ほど、男の息の根を止めようとしていた手から、剣がするりと落ちた。それは男を掠る事すらなく、無気力に地面に横たわる。
脱力し、姿勢の崩れた追跡者を、アトスは後ろから支えた。
アトスからは見えない表情。それは、彼女の背後にいるから、というだけではなかった。
後から駆けつけた護衛隊により、男は気を失ったまま連行されていった。ジュサックと何か話しているアトスを、アラミスは遠くから見ていた。
ただ、ぼうっと見ていた。
「じゃあアイツは、物盗りのシッポだったという訳か」
「ああ。尋問に耐えられるような男には見えなかったからな。すぐに、白状するだろう」
「そうか……」
納得しながら、ポルトスはこっそりと、アラミスの様子を伺う。それに気付いているのかいないのか、アラミスはただずっと、外へ顔を向けたままだ。トレビル邸のこの部屋へ戻ってから、ずっと。
今日の一件についてトレビルに報告した時も、アラミスは必要最低限の事しか話さなかった。たまたま通りかかった近くの家に物盗りの男が侵入しており、怒号と悲鳴に招かれるまま、男を追跡し、捕らえた。アラミスがトレビルに話したのは、ただそれだけであった。
「アトス」
小さな声で、アラミスが呼ぶ。固まっている部屋の空気に、動きを与えるかのように。
まるで別人のようなアラミスの声に、アトスは目を細めた。
「……何だ」
アラミスは振り返り、外に背を向けた。
「どうして、とめたんだ」
逆光を受けたその表情は、微笑を湛えている。
「どうして、とめたんだ?」
語尾をやや強めて、アラミスは再び言い放った。
「僕は手を汚すべきではないとでも、まさか、聖人だとでも思ってたのか?」
アトスの言葉を待たずに続ける。乾いた笑いを、張りつけながら。安らかな顔に、相応しくない言葉を。
「勘違いしないでくれ。僕は、悪人を斬って痛む良心なんか持ち合わせてないよ」
「何を言ってるんだ」
動揺するポルトスの静止も、アラミスには届かない。堰を切ったように、溢れ出した言葉の勢いは止まらない。
アラミスの脳裏には、物盗りの言葉が、こびりついて離れなかった。それは呪いの力を持ったように、彼女の心を灰色に染めている。
『お前、まるで女みたいな顔してるな! さっき俺が斬った奴の方がずっと、男らしい顔、してたぜ』
女のようだ、と言われるだけならば、構わなかった。銃士隊の門を叩く前から覚悟はしていたし、実際にそう言われる事も多い。
もちろん怒りを感じる事が多いが、それでも最近はその対処にも慣れてきていた。
「あんな物盗り、どうなったって構わないだろう」
あんな物盗り。私利私欲のために、殺生をした外道。それはまるで、彼女の愛する婚約者を殺めた仇と同じだ。
先ほどの男は確かに、恋人の仇ではなかった。
しかし。
(もし、仇だったとしても…アトスは邪魔をするんだ)
(そうだ、私は邪魔をされるんだ、仇討ちの邪魔を!)
「なんだよ。何がしたいんだよ、アトス」
気持ちが、怒りが、恨みが、憎しみが。言葉に乗って。止まらない。止まらない。
(フランソワは殺されたのに。私は女である事を捨てたのに。何も、何も知らないくせに!)
「あんな奴、あんな最低な奴を!生かしておくのが銃士だっていうのか!?」
そこまで言い放ってから、不安げに自分を見つめるポルトスの視線に、ようやくアラミスは気づいた。
はっとしたように、魔法が解けたかのように、彼女の表情は切り替わる。微笑が消え、少し青ざめていた。
「……すまなかった。何でもないよ。忘れてくれ」
早口でまくし立て、アラミスは窓から離れた。おぼつかない足取りで、退室しようとする。
アトスは立ち上がってから、アラミスの肩に手を伸ばし、掴む。アラミスはあっさりと動きを止め、自分を捕らえるアトスを力なく見た。
その瞳からはもう、怒りは見えない。怒りだけではなく、何も見えなかった。
「……あんな小物のために、君の手を汚す必要はなかった。……そういう事だ」
「そうだ。それに、白状させれば親玉もつかまえられる。第一、あれは護衛隊の管轄だしな」
「ああ……分かってる」
アラミスはポルトスにも、笑みを向けた。その表情は、いくぶん温かみを取り戻していたため、ポルトスは小さくため息を吐いた。
アラミスは、自身の肩にあるアトスの手を優しく振りほどき、ドアを開いた。
「ちょっと、頭冷やしてくるよ」
肩越しに告げ、静かにドアを閉めた。
トレビル邸の別室に入ったアラミスは、椅子に腰を降ろした。年季が入っている木製の椅子は、いくぶん体重の軽いアラミスが座っても、低い音を奏でた。
部屋には誰もおらず、誰か向かってくる気配も感じられない。その方が、今のアラミスにとっては都合が良かった。
机の上に両手を乗せ、息を吐きだした。その表情は、やはり晴れない。
(私だ)
まるで自分が発したとは思えなかった、不思議な感覚に導かれるまま紡いでいった、悪意に満ちた言葉。取り返しのつかない言葉。
(最低なのは、私だ)
物盗りに対しても、アトスに対しても。自分自身を制御できなかった事実を思い、アラミスは苦笑いした。
男を捕らえるのは自分達ではない。それが護衛隊の任務である事も、理解はしていた。しかし、感情が、その前に立ちふさがってしまったのだ。
物盗りの男と、婚約者を殺めた仇が重なってしまって、自分は―。
(何をやってるんだろう)
そうしてアラミスは、自分を不安げに見つめていた、ポルトスを思いだす。あの部屋を出る時、彼は小さくため息を吐いていた。もしかしたら、嫌われてしまったのだろうかと、アラミスは自嘲気味に笑った。
軽口を叩き合うまでに親しくなっていた気の良い男の前で、あのような醜態を見せてしまったのは初めてであった。もっとも、それはアトスも同じである。
しかも、アトスの場合は、その現場まで見られている。見られている以上に、止められてしまって。
(アトスが何故止めたのかは分からないけど。……でも)
あのような事を言うつもりなど、さらさらなかったのに。
「あんな、小物のために」
先ほど自分に向けられた、アトスの言葉を、小さく呟いた。自身に染みこませるかのように、言葉の意味を確かめるように。しかし、その意味は彼女の中で消化しきれていなかった。
後悔に包まれながらも彼女は、アトスの真意を掴む事が出来ずにいた。
アラミスは、自分の手を見つめる。手袋が外された手は、それでも白い。男を殴りつけた時に出来たアザが、指に残っている以外は。
アザなどは数日経たない内に消えるだろう。しかし。
(私の手は……こうして汚れていくのだろうか)
不意に、部屋のドアが開いた。新しい空気が流れると共に、最も会いたくて、最も顔を会わせたくない人物が姿を現す。
「ここだったか」
「……探して、いたのか?」
「ああ。だがきっと、この部屋だろうなと、俺は思った」
全く使われないという訳ではないが、それでも他の部屋に比べれば使用頻度が低い、トレビル邸の奥部屋。
そのドアを閉め、アトスはアラミスの隣に腰を下ろした。椅子はやはり、低く軋む。
「アラミス、すまなかった」
突然の謝罪。予想だにしなかったアトスの言葉にアラミスは目を丸くした。
(何故。アトスが謝る事なんて、ないのに)
「アトスは悪くないよ。君の言うとおりだったんだ。僕が悪いんだ、僕が、あんな奴に―」
「その事ではない」
アラミスの言葉を遮り、彼女の右肩をしっかりと掴む。
それは先ほど、退室しようとした時の比にならない程強いものであり、痛い位の力に、アラミスは狼狽した。アトスの方に引き寄せられた、気がした。
「あんな奴のために、君の手を汚す必要は無いと言った事だ。俺は嘘を吐いた。そんな理由などではない……君を、君を止めたのは」
突き刺すようなアトスの視線。その迫力にアラミスはうろたえながらも、逃げられないと思った。逃げてはいけないと、覚悟した。
ほんの少しだけ、アトスとの距離を詰める。
「相手がどんな奴だとか、そういった事は関係ない。本当は……怖かった。俺自身、怖かったからだ」
(な、何が……?)
胸中の問いに答える様に、アトスは続けた。
「あんな風に、敵に向かっていく君を。感情が走るままに敵を殺める君を、見たくなかったからだ」
「アトス……」
アトスが、自分を怖いと思うなんて。そう、思わせてしまっていたなんて。
かたかたと、アラミスの肩が震えた。それは非常に小刻みであるが、それでも、その小さな肩を掴んでいるアトスの手に、その動きはしっかりと伝わっている。
アトスは苦しそうに彼女を見つめ、もう片方の手も、反対の肩に伸ばした。小さな、小さなその震えを止めるように。封じるように。
だが、とアトスは続ける。
「それを邪魔したと、言うのであれば―」
「アトス!」
叫ぶように。今度は、アラミスが遮る。口腔内に渇きを覚え、目頭がほんのりと熱くなった。
アトスは戸惑いながらも、アラミスから視線を外さない。彼女の言葉を、ゆっくりと待つ。
喉までこみ上げるような気持ちを抑えながら、丁寧に、言葉を紡ぐ。真実の気持ちを。
「……僕は、君にそう思わせてしまった事が、一番、怖い……」
(手が汚れようと構わない。悪人を斬る事も、全然怖くない。でも、でも)
いつからだろう。
アトスとポルトス。彼らは良い先輩として、友として、尊敬していた。しかし、それ以上の感情など、あまり持ち合わせていなかった。
武芸に秀でており、王宮内部についても精通している。そんな彼らに取り入り、適当に付き合い、自分の力を高めていければと、仇討ちができればと。そう思っていただけだったのに。
個人的に親しくなりたいなんて、願ってなどいなかった筈なのに。
アトスやポルトスに嫌われていようが、どう思われていようが、自分の力にさえなってくれれば、それで良かったのに。
いつからだろう。
「アトス」
いつから、彼らに距離を置かれる事を、こんなにも怖いと感じてしまうようになってしまったのだろう。
「僕は、僕は二度と、あんな暴挙に出たりはしない。約束する。約束するよ」
偽りのない気持ちが、滑るように生まれ、それは言葉となって流れていく。
頬の力が緩み、アラミスは自然に微笑んでいた。無論、先ほどのような乾いた微笑みなどではない。
(ああ、私は、アトスやポルトスと一緒にいられる事が、嬉しいんだ)
いつからだろう、素直に、そう感じられるようになったのは。
肩の震えも止まり、アトスは安堵した。彼は手を離し、背筋を伸ばした。アラミスとの距離が、広くなる。
「そうか。良かった。……大丈夫だな。君を信じるよ」
それ以上の言葉は無用であった。目を伏せ、アトスも静かに笑った。
ようやく零れたアトスの笑顔が嬉しくて。アラミスはまた、気持ちが緩んだ。
「……アトス。ポルトスは?」
もう一人。大事な友がやって来ない事を不自然に感じたアラミスが尋ねた。
「ああ、アイツは、先に行っている」
「え?」
どこへ、というアラミスの疑問に、アトスは笑って答えた。
「ポンヌフの近くの料理屋だ。俺と……お前も必ず来るはずだと、そう言い切っていた」
その時の様子が、アラミスは容易に想像でき、吹き出しそうになるのを堪えた。
『アトスはアラミスの説得を頼む。俺は先に楽しませてもらうよ、もう腹が減って死にそうなんだ』とでも言っていたのだろう、と。
そして、一点の曇りもなく自分を信じてくれている、大柄な友人の心意気を思っていた。彼女は、先ほど感じた不安が、杞憂に終わりそうであると悟った。
(ありがとう)
「分かった。今日は僕がおごろう。迷惑をかけてしまった、せめてもの詫びだ」
アラミスの言葉にアトスは笑い、頷いた。
「行こうか」
「ああ」
どちらからともなく立ち上がる。椅子の軋む音が、二つ。
「今日の酒は、美味くなりそうだな」
アトスの発した言葉に、くすりと笑いが洩れる。いつもそうじゃないか、と言いたくなったが、アラミスはそれを心の中に留めておく事とした。
自分を信じている友人と共に、同じく信用してくれている友の元へ向かう。
到着する頃に、果たして料理はどのぐらい減っているのだろうか。そんな事を思うと、可笑しくてたまらなくなってしまって。先を歩いているアトスは不思議そうな表情を作る。
それでも、アラミスの微笑みは、止まらなかった。
(大丈夫、私は、大丈夫)
トレビル邸を後にした、その足取りは、もうおぼついてなどいなかった。
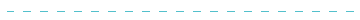
長い後書き
パノラマラウンジ最長小説は『少女を囲むは黄昏と』だったんですが、見事更新されてしまいました。おめでとう!
この話、「言葉」と「しかし。」って言葉が何回も出てきてますが…敢えてじゃないんです。ほかに良い言葉が浮かばなかっただけなんです…。
暴走アラミス&沈静化させるアトス(&ポルトス)を書きたいなと思って書いた話なので、あまり本編ストーリーとのリンクがないような…一応、時期的には、アラミスが正式に銃士となって少し経った辺りです。
『後輩として取り入って可愛がってもらう事で、自分の力を高めていければと、そう思っていただけ。』の下りは唐突過ぎたかなーとも思いましたが、ウチのアラミスはこんなんです。仲良しになろうがなかろうがどっちでも良いや、利用できるもんは利用しとけ!な感じで、打算的にアトス達と付き合い出してます。 (その辺は『少女を囲むは黄昏と』とかでも、ちょろっと書いてます)
パノラマラウンジの中ではかなり長い話でしたが、読んで下さり本当にありがとうございました!(2011/02/25)
![]()