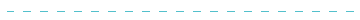
秋がいなくなる頃
部屋の外を歩く、大きな音が聞こえた。
ギシ、ギシ。年季の入った床をしっかりと踏みしめ、それは扉へ近付き、離れていく。
室内にいるアトスとアラミスは、その音がもう一人の親友によるものだろうと、頭の片隅でぼんやりと捉えていた。
勤務時間は終わったが、これで終わるのはきりが悪いと考え、アトスは本を読み進めていた。
そして遂に、最後のページをめくる。そこにあったのは、所有者のサインのみであった。それを視界に入れてから、アトスはゆっくりと本を閉じた。
まだ痛んではいないが、隊長のものだ。慎重に扱う必要があると彼は考えていた。
椅子は高い音を立てた。アトスは、アラミスのところに近付く。果たして彼女は、何か書き物をしているようであった。
「アラミス」
背後から声をかける。アラミスは手を止め、振り返った。
「これを」
アラミスの肩に乗せるように、先ほどの本を差し出す。アラミスは両手で、嬉しそうにそれを受け取った。
「もう良いのか?」
「ああ、さっき読み終えたばかりだ。慎重に扱ってくれ。読んだら隊長まで」
「分かった」
アラミスは机の中央に借り物の本を置いた。表紙には紺色の水玉のような模様が描かれている。
アトスに背を向けた彼女は再び筆を手に取り、紙に向かう。
「何を書いているのだ?」
背後から、アトスが覗き込む。そこには、手紙が置かれていた。こちらは、アラミスの字ではない。
「手紙の返事」
「手紙の返事?」
ゆるやかに復唱して尋ねると、アラミスは小さく息を吐いた。
「うん……恋文の」
「ほう」
アラミスが恋文の返事を書くのは、今回が初めてではない。時折こうして詰め所で書いていたが、それは久々の事であった。
返事は、毎回断りの内容であったが。
「それで、今回は受け入れるのか?」
「いや、断る」
「やはり、そうか」
アトスは苦笑いし、続ける。
「俺も人の事を言えたものではないが……アラミス、君は誰かと恋仲になりたいと、思った事は無いのか?」
「ないよ。仕事が充実しているからね、恋だのなんだのと考えていられないし」
それに、と呟いてから、アラミスは筆を置く。背後に居るアトスに構わず大きく背伸びをした。
振り返り、にこっと笑ってアトスを見上げ、きっぱりと言い放つ。
「もし恋をするとしても、追いかけられるより、追いかけたいからね」
感心したように笑うアトスを背に、アラミスは立ち上がって窓を開け放った。澄み切った空気が、秋の匂いを部屋に連れてくる。
「ん……随分と寒いな」
「昼間は温かかったけれどね。太陽が隠れてしまってから」
アラミスの指差した先には、雲に覆われて尚薄い光を放つ陽。快晴ならば、それは山の向こうから温かい輝きを放ち、パリの空を紅く染める時間なのだが。
「そうか……」
少し、決まりが悪そうに呟くと、アトスは帽子を手に、扉へ向かう。
「アトス?」
「俺はそろそろ帰るとするか」
「えっ、アトス?外套は?」
「……ばれたか」
振り返り、扉を背にした親友は、手を広げて笑う。
「昼間、温かかったからな。つい、置いてきてしまった」
「へえ、アトスにしては珍しいな」
言いながら、アラミスは自分の外套を手にして、アトスの元へ歩み寄る。
「使いなよ。外は寒いんだから。僕のだから、少し小さいかもしれないけど」
「しかし、君が着ていく分が、なくなるじゃないか」
「それは大丈夫」
彼女は、外套を押し付けるように渡す。アラミスは優しく微笑んで、部屋の隅にある外套を手にした。
「僕は用意周到だからね、二つ用意してあるんだ」
「何?」
アトスは思わず、トーンの高い声を挙げる。アラミスは楽しそうに話す。
「ふふふ、嘘だよ。君と同じさ。この前、ここにうっかり置いてきてしまって。
それで、家にあったもう一つを、今日は持ってきたという訳だ。今日は二つ持って帰るつもりだったのさ」
さも面白そうに笑うアラミスに、アトスも笑みが漏れる。
「そうか、それなら、ありがたく」
「ほらアトス、病み上がりなんだから、早く帰りなよ」
外套を戻したアラミスは、再び机に向かった。
「君は?」
「返事をまだ書き終えていないから、終わったら帰るよ」
「ありがとうアラミス。それじゃ」
ひらひらと手を振り、アトスの姿は扉の向こうに消えた。
扉が閉まり、アトスの軽やかな足音が、遠ざかっていく。アラミスは再び筆を置いて、静かに立ち上がった。
窓に近付き、庭を見やる。程なくして、自分の外套を羽織ったアトスが現れた。
窓で待ち構えていた事を始めから分かっていたように、アトスはすぐに振り返る。胸の前で手を振っているアラミスを見上げ、小さく手を振り返してから、門の外へ歩いていった。いつもの彼に比べれば、少し速い歩調。帰路を急がざるを得ない程に、外は冷えているのだろう。
風も吹いてきた。弱い風とはいえ、冷え切っているパリに吹くそれは、決して歓迎されるものではない。
(……)
思案を巡らせるように窓を見ていたアラミスは、また、机に戻る。
最後の文句をどうしようか。そんな事を考えていると、大きな足音が近付いてきた。足音は止まり、無遠慮に扉を開いた。
「よう!」
明るく、大きな声。ポルトスはずかずかと、筆を走らせているアラミスの傍に近付く。
ポルトスが隣りに立つと、アラミスは筆を置いた。それから、先ほど借りた本の横にあった、白い封筒を手に取る。
「なんだ、またご婦人からの熱い手紙か」
「ああ」
「で、また断るのか?」
「さっき、アトスも同じ事を言っていた」
おどけたように笑い、アラミスは丁寧に手紙を折る。四つ折りにされた手紙は、封筒にすっぽりと収まった。
慣れた手つきで、封を閉じる。
「断り文なのに、きれいに閉じて……几帳面だな、アラミスは」
「そうかな」
アラミスは立ち上がった。青い帽子を被り、髪の乱れを直す。それから、本と手紙を抱えるように持った。
「帰るのか?」
言いながらポルトスも帰り支度をしていた。部屋の隅にある、先ほどアラミスが手にしていた外套を取る。
勢いをつけて外套を払う。持ち主の体型に同じく、大きく広がった。ぐんと自身の後ろに回し、ポルトスは外套を羽織った。
彼が帽子を手にした頃、アラミスはいそいそと退室していた。
「アラミス?」
目をぱちぱちさせてから、ポルトスはその後を追った。
「アラミス、おい、待ってくれよ!」
トレビル邸を出たところで、ポルトスはアラミスに追いついた。
少し体を震わせながら、不思議そうな顔をしたアラミスは、ポルトスと向き合う。
「どうしたんだ?」
「どうしたんだ、じゃない。それじゃあ寒いだろう」
弱い風は、相変わらずさわさわと吹いている。雲の向こうから光を放っていた太陽も、今は遠く。
ひんやりとした風は、枯葉を遊ばせていた。一枚、二枚、三枚、四枚、それらはふわふわ浮いて踊る。
「うっかり、外套を忘れてしまったのさ。大丈夫だよ、すぐに帰れば」
「すぐに……って、これからご婦人のところに向かうのだろう?」
巨漢の友人の視線の先には、先ほど丁寧に封をした白い封筒。
「こんなの、渡すだけだから」
「俺が渡しておいてやるよ」
次の言葉をアラミスが言う前に、背中にほんの少しだけ温もりが宿る。
ポルトスが自身の外套をかけたのだと分かった時、手紙は彼の手へ抜き取られていた。
「お、おい!」
「俺は体が大きいからな、この位の寒さはどうって事ないさ。この手紙も渡しておいてやる。断りの手紙を渡すなんて、嫌な仕事だろ?
ええっと、このご婦人は……」
「か、返せってば」
アラミスは手紙を取り返そうと手を伸ばすが、体格の違いが大きく、とても届かない。
まるで子どもをあしらう様に、ポルトスは彼女から手紙を遠ざける。アラミスは困惑していたが、そんな彼女にお構いなく。
「おお!俺の家の近くじゃないか。だったら話は早いな」
大声で言うなり、ポルトスは身を翻し、走っていった。追いかけようとしたアラミスの足元に、外套が丸く落ちる。慌てて拾っている内に、ポルトスの姿はますます遠くなった。
そこでポルトスは振り返り、後ろ歩きをしながら、アラミスに向かって笑う。
「お前こそ、風邪ひくんじゃないぞ。また明日な!」
大きな腕で、大きく手を振ってから、前を向いて駆け出した。
「……」
アラミスはその場に立ち尽くしていたが、商人らしき男が前から歩いてきた事に気付き、ハッとしたように外套を羽織る。大きすぎて、外套を着るというより外套に着られている気がした。
外套は先ほどより温もりが薄れていたが、それでもこの寒空の下、彼女を風から守ってくれている。
(まさか……こうなるとは)
アトスに外套を貸すために吐いた嘘が、本当になってしまうとは。
(……しかし、何やってるんだろう、私たちは)
三人の間で、ぐるぐると巡る外套。色も大きさも異なるが、同じ思いの元に巡る外套。
それがなんだかとてもおかしくって、肩を震わせてくすくすと笑いながら、アラミスもまた帰り道を歩き出した。
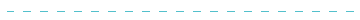
後書き
さわやか中高生のやり取りか!と自分で突っ込みながら書きました(笑)。仲良し三銃士シリーズでした。特にポルトスが凄く良い人でした。
アラミスが予備だと嘘を吐いたポルトスの外套ですが、アトスだったら気付きそうな気もしますけどね。「アラミス、それをよく見せてみろ」と言われて、あわあわするアラミスとか(笑)。
珍しくアラミスの策略(大げさ?)に気付かないのもまあいっかと思い、決行させました。 (2011/11/05)
![]()