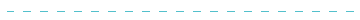
水入らずな夕方
「お父さん、ちょっとここに座って」
「どうしたんだ?」
コンスタンスは笑いながら、父の背中を押すように、椅子に座らせた。ボナシューはというと、服を注文したポルトスの家から戻ってきたばかりであった。
「この前まで大忙しだったでしょう?王妃様だけでなく、他の貴婦人の服も作っていたし」
そう言いながら、コンスタンスはボナシューの後ろに周りこむ。そして、小さくきれいなその手を、父の肩に乗せた。
「少し、押してあげる」
コンスタンスは手のひら全体に力を載せ、ぐいと肩を押す。
「お前も、疲れているだろう?」
机に手を乗せながら、肩越しに娘を気遣うが、コンスタンスはにっこりと笑う。
「良いの。私が、やりたいのよ」
「ああ、ありがとう。……お前も、こんなに強い力が、出るようになったんだなあ」
「うふふ、何言ってるのよ」
コンスタンスは、父の肩から手を離し、肘を乗せた。少しだけ強く、力をこめる。ボナシューは小さく顔をしかめた。
「いたた」
「ここ、ひどいわよ。相当根詰めて仕事をしたのでしょう」
「まあな。一度連れ去られて、仕事が遅れてしまったからな」
先の舞踏会に向け、ボナシューはアンヌ王妃のための衣装を丁寧に作っていた。その最中、ローシュフォールに連れ去られてしまい、謂れのない拷問を受ける事となってしまっていたのだ。
そういえばあの時は、ミラボー夫人が来ていた時、コンスタンスがどこにいたのかとしつこく聞かれたのだった。ボナシューはそれを思い出した。
ローシュフォールには、コンスタンスは出かけていたと嘘をついた。どうも、コンスタンスが家にいて、あの婦人から何かを盗んだという疑いがかけられていたからだ。
彼らは、コンスタンスがあの日、自宅にいたという証言が欲しかったようであったが。
(…………)
「お父さん、どうしたの?」
ふと黙り込んだボナシューを、コンスタンスは気遣った。その手は、きっちりと動かしたままに。
「いや……よく効くよ、コンスタンス」
あの日、コンスタンスが何をしたのか。というよりも、ダルタニャンが旅行へ行っていた数日間に、何があったのか。何も知らない。
だが、コンスタンスの事だ。何も間違いはないさ。聞く必要などない。私の娘なのだから。
笑みを浮かべて、ボナシューは目を閉じる。
押された箇所が少しずつ、解れていく心地よい感覚に包まれて。
「――お父さん、ありがとう」
「ん、どうしたんだ、急に」
ボナシューは目を開け、コンスタンスを振り返る。手を止めた娘は、照れたように笑っていた。
亡き妻に良く似た、心優しい顔。
「ううん。いつも、私の事を思ってくれて。私だけじゃなくて、ダルタニャンやジャンの事も。
ただ――体は、大事にしてね」
「ああ、ありがとう。もう良いぞ、お前も疲れるだろう」
「大丈夫だったら。あと少し、ね。そうしたら、今日はシチューを作ってあげる」
ボナシューもまた、安らかな笑みを浮かべ、再び前を向く。
ぐい、ぐい。コンスタンスは先ほどと違う箇所にあった凝りに、狙いを定めて押している。
(シチューか。そう言えばダルタニャンも、シチューが好物だなあ)
もうすぐ、仕事を終えて戻ってくる少年を思い、ボナシューは顔を綻ばせた。
肩に乗せられた温かい痛みに、安らぎを覚えて。
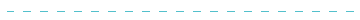
後書き
2011年父の日記念でした。17世紀フランスの人も肩マッサージはしていたのでしょうか。
ダルタニャン渡英について、ボナシューやマルトは結局知らされないままだった…という事でお願いします。
「お前も疲れてるだろ?」と2度も言ってるボナシューさん。ボナシューラバー、貴方のそういう優しさが大好きです。 (2011.6.19)
![]()