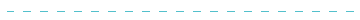
雨音
震えながら伸ばしてくる手を、私はそっと取った。空いている方の手で、必死に彼の体を支えながら。
崩れないで。倒れないで。私を置いていかないで。必死に気持ちをこめる。
ぽたり。ぽたり。水滴が私の髪から、彼の真っ赤な胸に落ちていく。
私は、彼の瞳をじっと見据える。彼も、私を見ている。豪雨が地面を叩き付け、遠くでは稲妻が落ちていた。
今から、何が起こるのだろう。私はそれを、知っている。
「しあわせになってくれ……きみにあえて、よかった……」
掠れた声でその言葉を紡いだ後、彼は瞳をゆっくりと閉じた。その体はズシリと重くなった。
その瞬間、自分の体が急激に冷えていくのを感じた。
ぽた。ぽたり。冷えた体に注がれる、冷たい雫。
幼い時にも、同じ事があった。私は、この人がどうなったのか、知っている。
信じられないけれど。受け入れられないけれど。
でも、この人は――。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
私は、ゆっくりと瞳を開けた。
外はまだ、雨。悪夢と同じ、雨。
うんざりしてしまった。再び、布団をすっぽりとかぶる。
雨から逃げるように。雨の音から、自分を守るように。
雨の日は、嫌い。
あの人がもういないという、その事実が、私の胸にこれでもかという程叩きつけられる。
雨の音が聞こえる日は、これでもかと言う程、思い知らされる。
雨の音に包まれ、あの人は息途絶えた。
雨の音とそれの連れてくる気温に、私はどんどん冷やされていく。身も、心も。
こういう日に見る夢には、決まってあの人が出てくる。冷たくなっていく、あの人が。あの悪夢が。
だから、嫌い。大嫌い。はやくいなくなれ。いってしまえ。
グッと目を閉じ、雨から隠れていた。
その時だった。
「おーい!」
遠くから、聞きなれた声が私を呼んでいる。その声と、大きくなった雨の音が室内に飛び込んで来た。
それからすぐに雨の音だけ小さくなり、声ははっきりとしたものとなって、私の耳に届く。
「おーい!アラミス、いないのかー?」
それは、この声の主が、室内に入ってきたことを意味する訳で。
私は慌てて体を起し、ベッドから離れた。寝ているところなんか見られた日には、この友人に要らん心配をかけてしまう。
ああ、耳障りな雨の音が、耳に届いてしまう。けれどもそれどころではない。集中しろ。落ち着いて、落ち着いて。
ドアへ駆け寄り、乱暴に開けた。階下の友人に向かって、言い放つ。
「どうしたんだよ。ああ、びしょ濡れじゃないか」
「うまいもの持ってきたんだ。一緒に食おうぜ!」
ポルトスはそう言って、何か食物が入っているらしいカゴとワインを揺らした。屈託のない笑みを向けながら。
私は自室へ戻り、タオルを取り出した。大きめのものだ。むしりとる様に手にし、部屋を出ようとしたところで、タンスへ引き返す。そうだった、あの大男が、一枚ごときで足りるものか。
二枚、三枚、四枚、五枚。手に抱えるほどとって、部屋を出る。階下の友人に投げつけた。
「ぶふっ」
「それで体ふけよ。カゼひいちまうだろ?」
顔面で三枚、残り二枚を頭上で受け、ポルトスはまごついた。階下に降りてきた私は、ポルトスの手から、籠とワインを奪うように取り上げ、テーブルの上に乗せる。
置いてからすぐに、ポルトスの前へ回り、顔面のタオルを彼の手に乗せる。乗せるというより押し付ける、といった方が正しいか。
「へへっ、ありがとうよ」
にへら、と笑ったポルトスは、タオルを使って頭を拭きだした。
雨の音は、まだ聞こえている。屋根を打ち、壁を弾いて、地面に落ちる。いくつも、いくつも。
それらの耳障りな音は、私にしっかり届いてしまっている。不愉快極まりない、悪夢の音。
しかし、この友人の来訪は嬉しかった。人がこんなに嫌な思いをしているというのに、何か食べようだなんて、のん気な話を持ってきて。
何でも良いんだ、この陰鬱な気持ちを紛らわしてくれるのなら。布団にくるまってじっと耐えているより、ずっと良い。
「少しは乾いたか?」
「ああ。助かったよ。料理を死守してきたからな。自分の事は気遣ってなかった」
それでカゼなんかひいちまったら、せっかくの食べる楽しみも減ってしまうけどな。彼は笑いながら付け足した。
私もある意味助かったから、良いのだけれど。
私たちは向かい合って、食事を始めるところだった。ポルトスが持ってきたのは、パンと、イノシシの丸焼き、それからぶどう酒だった。
「へへ、俺様が死守したお陰で、料理の方は全然濡れてないな」
確かに、ずぶ濡れだったこの男と対照的に、料理には―全然、という程ではないが―水滴はほとんどついていない。本当にこの大雨の中を通ってきたのだろうか、という程に。
彼は、パンにナイフを走らせる。
「うまいもん食ってると、イヤな事も忘れるもんだな」
「イヤな事?」
「そうだな、仕事で失敗したとか、恋に破れたとか、そういった事なんかをな」
「食って忘れられるのか?お前は」
私は、ため息混じりに言ってのける。ぶどう酒をグッと飲んでから、ポルトスは続けた。
「ん、まあな。食ってる間はな。いいじゃないか、しんみり食うよりも、イヤな事を忘れて楽しんで食ったほうが、料理だって嬉しいに決まっている」
私は彼の持論に思わず笑ってしまう。イヤな事がどうとかではなく要は食べられれば良い、という気持ちは凄くよく伝わってくる。
それよりも、気になることがあった。
「ポルトス……何かあったのか?」
「なにが?」
「そんな事言うなんて。まるで、何か嫌な事があったような言い方じゃないか……」
「いや、そういう訳ではないのだが」
そう言って、ポルトスは丸焼きを一切れ、口に運んだ。いつの間にか、パンは半分無くなっている。こいつ、私の分を残すつもりがあるのか。
「なんとなく、言ってみたかっただけだ。誤解させちまったか」
「いや、それなら良いんだが」
なんだ、いつものポルトスか。いつもの、大らかで、気さくで、分かりやすい。
いや。もしかして、雨によって運ばれてしまった陰鬱な気持ちが、私の気持ちが読まれてしまっていたのだろうか。顔に出ていたのか。
誰にも心配などかけたくはない。特に、この男には。こいつだけには、絶対に知られたくないのに。
私は、ぶどう酒に口を付けてから、恐る恐る尋ねることにした。その理由を。もちろん、顔にはいっさい出さないように。
「ポルトス」
「ん?」
「どうして、俺と一緒に食事をしようと思ったんだ?」
「どうしてって……」
ポルトスは半分呆れたような、拍子抜けしたような声を出した。ナイフを持ったまま答える。
「そりゃあ、お前が友だちだからだろ。何言わせるんだ」
そう、さらっと言ってのけた。
友だち。信頼し合い、助け合い、どんな時でも支え合える。
ああ、そうか、そうだった。彼は、絶対的に私を信頼している。そして、私も―。
「そうか、そうだよな……ゴメン、変な事を聞いた」
おかしくなって、笑ってしまう。
私も、信頼している。絶対的に信頼している。
おかしな疑いを持ってしまったものだ。ああ、そうだ。彼はこういう人だった。
気持ちを読むとか、顔を読むとか、そういう事じゃない。ただ、友だちだから、したい事をしたのだと。
そういう人だ。この大きな人は、そういう人だ。
「どうしたんだ?アラミスこそ、何かあったのか?」
ポルトスはナイフを片手に、心配そうな声を向けてくる。私は、笑って答えた。
「いや。雨が降ってるからかな。おかしくなっちまったのかも」
嬉しかった。信頼できる人がいる、いてくれる。それがとても嬉しかった。
私は、自然に笑っていた。大嫌いな雨の日に、心の底から笑っていた。
悪夢とは関係のない人。雨の日とは関係のない人。それなのに―否、だからこそというべきか。他愛もない話を笑ってできることが、嬉しかった。
皿は空になってしまったけれど、こいつとの話はまだ弾む。私は嬉しくて、続けて話してしまう。
不信がられるとか、考える必要はない。
こいつは、一緒に食事をしたかったから、私の家に来た。だから、私も、こいつと話したいから、そうするのだ。
雨の日は嫌い、大嫌い。それが変わった訳ではないけれど。
こうして、雨の音に嬉しい思い出を重ねていけたなら。
少しずつ、少しずつでも良いから、そうしていけたなら―。
降り続く雨は、まだ止みそうにない。
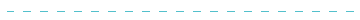
後書き
昔発表していたものとタイトルは同じです…が、内容を改造して長くなりました。あ、でも、癒し系ポルトスと雨音嫌いなアラミスというテーマ(?)は変わってないです。
時系列は、アラミス入隊2年目とかそのぐらいです。ダルが登場するよりずー…っと前。
雨音を聞きたくなくて、布団をかぶってうずくまるという、ちょっと普通じゃないアラミスは書いてて楽しかったです。
癒し系ポルトスのお陰で、アラミスは大嫌いな雨の日を楽しく過ごせました、と。まとめるとそういう話です…。 (2010/05/28)
![]()